アイデアをカタチにする楽しさを伝えたい!ヨシヒロです。こんにちは。
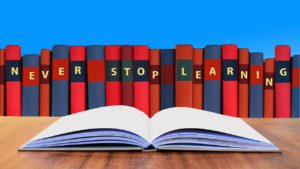
目次
インプットよりアウトプットしよう!
さて今回は様々なノコギリをご紹介します!が、その前にちょっと前置きのお話を・・・(すぐに本題を読みたい方はこちらをクリック!該当部分へジャンプします。)
さて、DIYアドバイザー資格の取得を目指して勉強をはじめました。試しに何も勉強しない状態で過去問を解いてみたら、な、な、なんと!ほぼ0点!笑 これはまずい・・・というか、難しい。教科書を読んでいても全然頭に入ってこないので、アウトプットしながら楽しく勉強したいと思います!
最近私が学んだ大切なことは、インプットよりもアウトプットの方が大事だということ!どれだけ知識を詰め込んだって使わなきゃ意味ないし、インプットするだけではただの自己満足で終わってしまいます。だから、アウトプットすることが大事。ブログ記事を書くことも、私にとってはアウトプットの一つです。
私のブログを読んで、へぇそうなんだ!という気づきを何か一つでも得ていただくことができれば、私にとってはとても嬉しいことです。アウトプットした意味があります。ということで、教科書を読むだけじゃつまらない勉強も、こうやってブログでアウトプットしながらやってみたいと思います!
ブログにアウトプットしておけば、インターネットさえつながればいつでもどこでも記事を読めます。思い教科書を持ち歩かなくても、スマホ一つでどこでも勉強できるわけですね。もしあながもDIYアドバイザーを取得しようと考えていらっしゃるのであれば、この記事がきっとあなたの勉強のお役に立てるはずです。
DIYツールってこんなにもあるのか!
ということで今日は、DIYツールってこんなにもあるのか!シリーズ第1弾。ノコギリ編です。私が読んでいるDIYアドアイザーハンドブックには様々なツールが紹介されています。その中の木工用ノコだけでも、両刃ノコ、替え刃式ノコ、胴付ノコ、畔引きノコ、廻しびきノコ、ファイルソー、ツッキリソー、折り込みノコ、手曲がりノコ、仮枠ノコ・・・とたくさん紹介されています。
そ、そんなにあるのか!知らなかった(T0T)DIYの世界も奥が深いなぁと思います。ということで今回は、いろんなノコギリを紹介します!ここでは、DIYアドバイザーハンドブックに掲載されているノコギリを全てご紹介!大別すると、木工用、竹用、多目的の3種類です。
木工用ノコ
まずはDIYerが一番よく使うであろう木工用から。なお、以下にご紹介するノコギリで「そうそう、これを探してたんだよ!」という方のために、すぐに楽天市場やAmazonの販売サイトへも移動できるようにリンクを貼ってあります。どうぞご利用ください!
両刃ノコ
たぶん、ホームセンターとかで一番よく目にするノコギリがこれ。両刃の片側は木目に沿って切る縦引き用、もう片方は木目に垂直に切る横引き用になっています。刃の部分をよ〜く見ると形が違うのが分かりますよ。
替え刃式ノコ
替え刃式ノコは、文字通り刃の部分を交換できるタイプです。主に板材や角材の切断に使用します。メーカーによって刃の形状やグリップ(持ち手)の形など様々なものが市販されています。自分の使いやすいグリップが見つかったら、あとは替え刃をいくつか用意しておいて用途別に使う、というのは作業効率が上がりそうですね。
胴付ノコ
胴付(どうつき)ノコは、刃の背の部分に補強材のようなものが付いています。これによって、例えば継ぎ手などの精密な加工が必要な部分を加工するのに適しています。木工をやり始めたら一度はやってみたくなる次手作り。そのためにはこの胴付ノコが不可欠ですね!
畔びきノコ
畔(あぜ)びきノコは、材料をくりぬいたり溝を掘ったりするために使うノコギリです。っていうかなんじゃこの形は!って最初は思いました。恥ずかしながら、長年DIYをやっていますがこんな道具は知りませんでした。溝を掘るのはノミとハンマーで頑張って加工していましたが・・・これからはコレ使おう!
廻しびきノコ
廻しびきノコは、曲線状に引き抜いたり、透かし彫りの引き抜きに使われるノコギリです。だんだんとマニアックなノコギリになってきましたね・・・。きっと透かし彫り大好きなDIYerさんは持っているのでしょうが、一般的な家庭にはなかなか無さそうなノコギリですね。
ファイルソー
ファイルソーはオーディオスピーカーやパイプなどの穴あけ作業用の工具です。これまたあまりお目にかかることの少なそうな工具ですね。工具の世界は奥が深い・・・でも穴を開けたいシーンは時々あるので、1本持っていると重宝するかも?
ツッキリソー
ツッキリソー。名前がいいですね(笑)。きりと廻しびきノコの二役を担う便利なやつだそうです。電気工事、配管工事、換気口などの穴あけ作業に使われるもののようです。例えばエアコンの取り付け業者さんなんかは必須アイテムなんですかね?
折り込みノコ
マニアックなノコギリが続きましたが、ここにきてようやく私も持っているノコギリが登場!折り込みノコ。刃を折りたたむことができますので、コンパクトに収納できるのが便利です。私は木工小細工用に使っていますが、植木の剪定、枝切り、花道の枝切りなどにも多用されるようですね。確かに庭師さんなんかは動き回りながら作業されるので、コンパクトに畳んでポケットにしまえる機能は必要な気がします。
手曲がりノコ
手曲がりノコ。文字通り、持ち手部分が刃に対して曲がったようになっています。主に丸太や生木を切るために使われるノコギリとのこと。刃は横びき用で目詰まりしにくい大きめのものが付いているらしい。丸太を切ることはまずないな・・・一度は切ってみたいけどね。
仮枠ノコ
仮枠ノコ。これも用途特化型の道具です。建築現場でコンクリートを流し込む作業の時に、コンクリートを整形するための木枠を使いますが、その木枠を切るノコギリですね。狭い場所でも作業しやすいようにノコ身が細いのが特徴です。
ここまで、主に木工用のノコギリでした!これだけでもお腹いっぱい感ありますが、まだまだノコギリの世界は奥深い・・・以降は竹用、多目的用途のものなどご紹介していきます。
竹びきノコ
私は竹細工をすることはありませんが、竹を切りたい人は必須の道具でしょう。見た目は木工用と大差ありませんが、刃先は竹の強い繊維を横びきで切れるように細かく短く作られているそうです。職人さんなら刃先を見るだけで違いがわかるんでしょうね。きっと。
多目的ノコ
ここからは多目的用途のノコギリです!ここまでの木工用だけでもすでに多目的感がありますが・・・まだまだいきますよ!でもノコギリの話ばかりでちょっと疲れたよ・・・という方は、木のある美しい風景でも眺めてちょっと目と頭を休めてくださいね。


糸ノコ
糸ノコは小中学校の授業で使ったことがある人も多いのではないでしょうか。木材の曲線カットに使います。弓のような形をしていて、刃の種類を変えることで金属板の切断も可能です。最近は卓上で電動のものや、木材の曲線カットにしてもジグソーなどの電動工具が主流かもしれませんけどね。
ダボ切りノコ
ダボ切りノコ。ダボとは、木材同士をつなぐ円柱状の木の棒のことです。木ねじの穴を隠すのにも使ったりしますが、その際、表面から飛び出した不要なダボを切断するのに使います。刃が薄くペラペラで、しならせながら使うことができるので、面から突き出した突起物を切断するということに威力を発揮するノコギリです。私も使ってます。
金切りノコ
文字通り、金属を切るためのノコギリです。形状は木材用のものと同じような形のものもありますが、私はこの糸ノコのようなU字型(?)タイプを見慣れているのでこちらをご紹介。機能としてはどれも同じと思います。木工細工に金属のパーツをちょっとプラスするだけで、なんかランクアップした気になれます。木材しか切ったことがない・・・という方は、これを使って金属の加工にも挑戦してみましょう!
フレキシソー
別名ワイヤーソーとも言いますが、刃の付いたワイヤーで金属、プラスチック、木材の切断が可能です。ポケットに入る!なんて書かれて売られているみたいですが、うっかりポケットに手を突っ込んだら手が血だらけ・・・なんてことを想像してしまいます。使われるときはくれぐれもご安全に!
新建材ノコ(デコラソー)
木材でも金属でもない、デコラ板(メラミン樹脂)のような素材を切るのに使われるノコギリです。これもほとんどのDIYerは使わないのかもしれませんが、住宅のリフォームなどをされる方は必要かもしれませんね。
パイプソー
塩ビ、プラスチック、サイディングボードなどの切断に適した目の細かいノコギリです。目が細かすぎて、逆に木材の切断には向いていません。木工用のノコギリで塩ビパイプなど切れなくはないですが、切り口がボロボロになっちゃいますので、このような専用工具を使うのがオススメです。
ミゾキリソー

ミゾキリソーはその名の通り、溝を掘ったり、面取りやけがきなどにも使われるノコギリだそうです。上の写真は鋸職人さんのHPに掲載されているものを拝借いたいました。職人さんしか使わないような珍しいノコギリかもしれません。Amazonでささっと探した感じでは見つかりませんでした。
断熱材カットソー
こちらも名前の通りですが、断熱材専用のノコギリです。分厚くて柔らかいものを切るのに適しているのですね。他の鋸に比べれば刃の形がかなり違いますね。発泡スチロールなんかも切れるやつだと思います。
終わりに
ということで、色々なノコギリをご紹介させていただきました。ホントに色々あるんですねぇ・・・DIYアドバイザーの勉強を始めたことをきっかけにちょっとディープなノコギリの世界に浸ってみました。あなたももしお気に入りの1本があれば、ぜひ使ってみましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
























